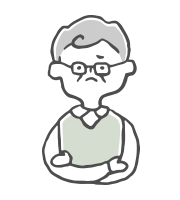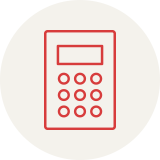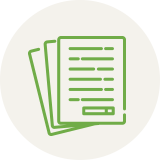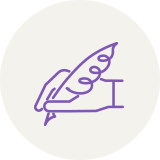【司法書士が解説】相続手続ワンポイント「よくあるミスと、よくあるお問い合わせ」
多岐にわたる相続の財産承継手続について、よくあるミスや、よくあるご質問を短くまとめてみます。もしご自身で行うのであれば、ぜひ気にしてみてください。いろいろと気にしないといけないのだな…と思われた方は、ぜひ専門家を頼ってみてください。
登記編①道路漏れ
不動産登記で、ご自身で登記をされた際に、よく起こってしまうミスが、道路漏れ。
不動産の相続登記の際、固定資産税納税通知書を元に、どんな不動産があったかピックアップをする方がほとんどがと思います。地目が公衆用道路、となっている土地は、固定資産税が課税されていないことがありますので、納税通知書の物件一覧からは漏れてしまうのです。また、近隣の数軒で私道を持分で持ち合っているところもあります。これも、漏れやすい。
漏れたまま、数十年放っておかれることもざらにあります。どこで気づくか、どこで困るのか。それは、売却するときですね。売却するときに道路の名義が変わっていない。こうなると、きちんとした価格で売れなくなってしまいます。再度の遺産分割協議に協力してくれない相続人がいたりすると、大変です。登記の際には、道路漏れにご注意を。
登記編②権利証は相続登記にはいらない
権利証が無いんです。
ご相談の際に、権利証が見つかりません。権利証が無いと相続登記できないですよね。
と聞かれることがよくあります。
相続登記の際に、権利証は不要です。なので、見つから無くてもOK。
権利証は添付書類になっていないのです。
ただ、物件の漏れを確認するためには、きちんと見ておくべきなので、お手元にあればご相談の際には持ってきていただきたいですが、無ければなくてもOKなのです。(ただし、例外として遺贈すると記載された遺言書をもとに登記をする場合には必要になります)
登記編③被相続人の最後の住所と登記簿上の住所
基本的に、不動産の相続登記に必要な書類は、預貯金などの手続きをする際の書類とほぼ一致します。なので、ご自身で預貯金の手続を行った後に、その際に使った戸籍や住民票、印鑑証明書を持ってきていただければ、相続登記に使うことができます。ただし、一つだけ銀行では要求されないけれど、登記の際に必要になるのが、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所のつながりを示す、住民票の除票や、戸籍の附票、です。登記簿に記載されている所有者の住所と、亡くなった時点での住所の一致を確認するための書類です。もし、引っ越しなどをしていて、住所が異なっている場合には、住民票や戸籍の附票の過去の住所の履歴に、登記されている住所が載っていること、が原則必要になります。
登記編④書類の期限
預貯金の解約手続で利用した書類を、登記で使いたいのだけど、だいぶ古いんだよね。期限過ぎちゃってるけど大丈夫?とのご質問をよく受けます。相続登記申請する際には、印鑑証明などの添付書類に期限はありません(『遺贈』などの一部例外を除く)。数か月前のものでも、数年前のものでも、登記には利用可能です。(ただ、相続人の戸籍や住民票は、変更があるといけないので、あまりに古い場合には、最新のものをとっていただく場合があります)
ちなみに、相続登記は令和6年4月1日から義務化されております。それより前の相続をそのまま放っておいてある方は、令和9年3月末までに登記をしなくてはなりません。
もし、お手元に預貯金解約の際に使用した戸籍等がある場合には、それがそのまま使えますので、ぜひ登記にもご利用ください。
登記編⑤地方の物件漏れ
地方にある祖父母の実家、あるはずなんだけど固定資産税来てないんだよね。
その他、原野商法、リゾート地商法等で昔買ってしまった土地があるけど、固定資産税が来ていないからどうなっているか分からない…、最近はそんなお話をよく聞きます。
固定資産税には免税点というものがあり、評価額が一定の金額以下ですと、そもそも固定資産税がかかりません。かかっていないからと言って、登記しなくて良いかというと、そういうわけではありません。やはり、令和6年4月1日からの相続登記義務化の対象です。そのまま放っておいてある方は、令和9年3月末までに登記をしなくてはなりません。気になる方は、権利証を探してみたり、土地があるかな…という市区町村に名寄帳登録事項証明書の請求をかけてみたりして、調べてみてください。なお、令和8年2月2日から所有不動産記録証明制度(→相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度)が始まりますが、これによってきちんと調べられるようになるのは、だいぶ先になると思われます。
この記事の執筆者

- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
-
保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
横浜・港北で主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
港北・新横浜で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで