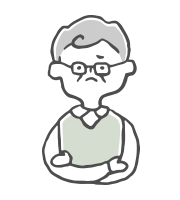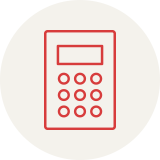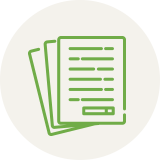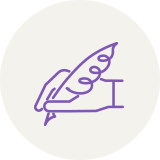シリーズ遺言書のススメ ~あなたが遺言を“書けない”7つの理由~
目次
遺言書、どんなイメージを持っていますか?
『⽼い⽀度』なんて⾔葉で語られることもありますが、まだまだアクティブな⽅々にとっては、
もっと先のイメージのもの・・・、あまり自分には関係のなさそうなもの・・・、でしょうか。
でも、まだアクティブなうちに、遺言書をぜひ検討してほしいと思っております。
ほんの⼀部、遺言書がなくても良い方はいますが、多くの方にとっては、遺言書はあった方が良いものだと考えます。
しばらくの間、日々のご相談の中で、皆様が遺言書の作成に踏み切れない理由としてよくある誤解や疑問を、ご紹介していきたいと思います。
このコラムを書こうと思ったきっかけは、とあるセミナーです。
このセミナーは、区役所に隣接する公会堂をお借りして税理士さんと連携して⾏うもので、
30〜40名が満員、そしてとてもリピーターが多いことが特徴です。
そこで、遺言など終活関係のお話をさせていただくのですが、
毎回アンケートには『遺言の大切さが分かった』などのお声をたくさん頂戴します。
うれしいことです。
しかしながら、次の回、たくさんのリピーターさんを前に、その後遺言に着手した方がいるか聞いてみても、全く手が上がらない・・・
大切だとは思っても、なかなか腰が上がらない、書く気にはならない??
この繰り返しです。
(私のお話に説得力・パワーが⾜りない、というのは置いておいて・・・笑)
それから、『遺言書を書くべき理由』と同じくらいに、『遺言書を書けない理由』『遺言書を書けない理由』を集めたら、そしてその理由を取り除いたら、みんな遺言書を書いてくれるかな、と思うようになりました。
『書けない理由』『書けない理由』、をどんどん掘り下げていきたいと思います。

あなたが遺言を’書けない’理由①
『預金なんて、これからも生活費やら病院代やらでいくら残るかわからないんだから、今は遺言には書けないよ』
これは遺言の作成のご相談を受けている中でも、よく聞くセリフです。
・遺言書には、預貯金の金額まで記載しておかなければならない
・遺言書に記載した財産は、必ず残しておかなくてはならない
この2つの誤解があるものと思われます。
遺言書には、金額までは記載する必要はありません(分割方法によっては、記載することもありますが…)
当然ですよね。遺言書を書いた時の金額を書いても、入金があったり引き落としがあったりで、日々金額は変動してしまいます。
誰も、相続発生時の残高の予測なんてできません。
遺言書には、通帳の金融機関名や口座番号だけ、書いておけばOKです。
覚えておいてくださいね。
あなたが遺言を‛書けない’理由②
『遺言を書くほど財産がない』
これも多い『書けない』理由です。
確かに、一昔前までは、遺言書は一部の財産持ちが書くものだ、というイメージがあったようです。
今も、そのイメージを引きずっている方も多いようです。
ただ、全く財産の無い方って、ほとんどいないんです。
おそらく少なくとも一つはご自身名義の通帳があるはず。
それは立派な財産です。
そして、財産の無いほうが、揉めた場合に解決策が少なくて困ってしまうことがあります。
(財産が多ければ、分け方の選択肢も増えることが多い)
ちなみに、裁判所ホームページで公表されている司法統計から、令和4年度に認容・調停が成立した遺産分割事件の遺産価額ごとの件数をみると、約3割が遺産の総額が1000万円以下となっております。
また、遺言に書くことができるのは、財産に関してだけではありません。
認知をしたり、祭祀を主宰すべき者を指定したりすることもできます。
そして、付言といって、相続人に向けて何らかのメッセージを載せておくことも可能です。
特に、ご結婚されている女性の方については、財産は全て夫の名義なので関係ない、と思われる方もいるようですが、
ご自身名義(妻名義)の預金もあるはずです。
また、夫が亡くなった後、相続する分があるはずです。
もちろん、その後に遺言を書けばよいですが、その時には認知症になっている可能性もあります。
そうなると、遺言書も作れません。
これからもらう財産を想定して、遺言書を作ることも可能ですので、配偶者が遺言書を作る際には、是非ご自身の遺言書も一緒に検討してみてください。
あなたが遺言を‛書けない’理由③
『うちは家族の仲がいいから、遺言がなくても揉めないよ』
これも遺言を書けない方の、常とう句ですね。
確かに、相続人全員が円滑にコミュニケーションをとれて、遺産分割協議がきちっとまとまれば、
何の問題もありません。
両親のうち、片方の相続の際には揉めなくても、両親とも亡くなってしまった場合に揉めた、なんてことは多々あります。
表向き仲が良いように見えても、例えば「押し出しの強い長男に、次男が気を使って自分の言いたいことを言っていない」ことで、仲が保たれているだけかもしれません。
また、仮に法定相続分に従って分ければ良い、という想いであっても、
親が指針を示してあげているのと、そうでないのでは、残された人たちの心理的な負担も変わってきます。
また、実家を売却して分けても良い、というお気持ちであれば、そういったことも書いておくと良いかと思います。
また、遺言書は争続を防止する、という効果だけではなく、相続の際の手続がスムーズになる、というメリットもあります。
最近ですと、例えば相続人である子どもの中に、海外居住者がいる場合など。
日本に住所のある方であれば遺産分割協議書には印鑑証明書を添付しますが、
日本に住所がない場合には領事館などでサイン証明を取得することになります。
印鑑証明であれば、それこそ今はマイナンバーカードを使ってコンビニでも取れますが、
国によっては、領事館まで数時間・・・なんで場所もあると思います。
残された方の手間も、気持ちの負担も、遺言書があることで、きっと少なくなりますよ。
あなたが遺言を‛書けない’理由④
『遺言書って作るのにたくさんお金がかかるんでしょ?』
こちらも良く聞きます。
確かに、コストのかかる遺言書もあります。
公証役場で作ってもらう公正証書遺言。
こちらは、以下のとおり作成時に公証役場手数料を支払う必要があります。
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12
(日本公証人連合HPより)
財産のボリュームと、分け方によって、手数料が決まってくるわけです。
よって、人それぞれなのですが、だいたい5~10万円前後くらいの金額になることが多いような気がします。
さらに、直接公証役場とやり取りをすれば、上記の金額のみで済むのですが、公証役場は内容に関しての(細かい)アドバイスまではしてくれません。
また、どんな資料を提出すればよいのか、分からない方も多いかと思います。
弁護士、司法書士や行政書士、税理士に公正証書遺言作成の手伝いをお願いすると、公証役場との事前のやり取りは全部お任せにできます。
内容に関してのアドバイスもしてくれます。
ただ、当然ですがここにも手数料が発生してしまいます。
この手数料は事務所によって異なります。
ちなみに、当事務所は、内容にかかわらず一律98,000円(消費税込107,800円)です。
そうすると、公正証書遺言作成には、公証役場手数料10万円(仮)+司法書士手数料107,800円で、約20万円程度かかることになります。
確かに、安くはないですね。
ただ、この金額は、相続人が揉めること・そしてそのためにかかるコスト と 天秤にかけて検討してください。
もし、遺産分割協議がまとまらず争いになってしまった場合は、これ以上のお金(弁護士費用等)や時間がかかる可能性がありますので。
そして、コストの気になる方は、コストのかからない遺言の方法もありますよ。
それは自筆証書遺言です。
自分ですべての文章を書き、日付と氏名を記載して、捺印する、そんなスタイルの遺言です。
こちらの遺言については、近年法律の改正で、どんどん利用しやすくなっています。

あなたが遺言を‛書けない’理由⑤
『遺言書って作るのにたくさんお金がかかるんでしょ?』その2
さて、今回は自筆証書遺言のお話です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自ら書き、これに印を押すことで成立します。
原則として、全文を自分で書かなければならない、という点が重要です。
『文章をパソコンで作成して、最後に署名捺印』では、遺言書として成立しないので要注意です。
但し、最近の法改正で、財産目録の部分は、自分で書かなくても良いことになりました。
財産目録をうまく使えば、自分で書く部分は、大幅に減らすことが可能です。
参考
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
良く、自筆証書遺言と公正証書遺言の比較で、『自筆証書遺言は簡単に作れて』『公正証書は作るのが大変』としているものがありますが、これは正直疑問です。
意外と、全文を自分ですべて書く、という行為は、ハードルが高いものです。
シンプルな内容のものであれば、そうでもないかもしれませんが、遺産分割の方法が複雑になればなるほど、書く量も増えます。
そして、意外と遺言書を書くぞ、とペンを握ると、緊張するものです。
私も、後述する自筆証書遺言の保管制度を試してみるために、自分で遺言書を書いてみました。
そんなに長い文章ではなかったですが、何度か間違えて書き直しました。
気づかないうちに肩に力が入っていたのかもしれません。
(訂正の仕方もちょっと特殊なので、できれば書き損じたら、最初から書き直すことをおすすめしています)
その点、公正証書遺言は、事前の準備や段取りはあるにしろ、遺言者は署名を1箇所、捺印を1箇所するだけです。
事前の準備や段取りは、司法書士や、場合によってはお子さんたちに任せることも可能です。
どちらが楽かと聞かれれば、ケースにもよりますが、公正証書遺言の方が楽なことが多いと思います。
では、自筆証書遺言のメリットは、何か。
やはりコストにあるかと思います。
紙とペンさえ用意して自分で書くのであれば、コストはかかりません。
また、今では書いた遺言書を法務局に預けることが可能ですが、
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
↑ 様々なメリットがあります
これにかかるコストは3,900円のみです。
例えば、『すべての財産を配偶者に』なんていうシンプルな内容であれば、
わざわざコストをかけずに、自筆証書遺言を選択するものありだと思います。
ただ、できれば書いたものは一度、専門家の目を通してください。
コストを意識した結果、きちんとした遺言書になっておらず、望んだ結果にならなかったり、何十倍もの損害が発生してしまうなんてこともあります(てにをはを間違えたが故に、数百万円の損害になってしまった例もあります)
当事務所では、自筆証書遺言作成のご相談・案文作成・自筆証書遺言保管制度利用のための申請書作成も含めて、
一律49,800円(消費税込54,780円)で対応しております。
こちらのご利用もぜひ、ご検討ください!
あなたが遺言を‛書けない’理由⑥
『まだ若いから・・・』
確かにそう思いますよね。
何歳になったら遺言書を書くべきか、これは悩むところではあります。
年齢というよりも、それぞれが置かれた家族の状況による、といったところでしょうか。
例えば、50代であっても、離婚を経験していて前の配偶者との間に子どもがいる方は、書いておくべきでしょうし、
80代であっても、すでに配偶者を亡くしていて、子どもが一人。
子どもにすべてを継がそうと思っている方は、書く必要がない、ということになるでしょう。
でも実は、若いからこそ書いておいた方が良いケースもあります。
例えばこんなケース。
夫が亡くなった際に、お子さまが未成年だと、遺産分割協議をするためには、裁判所に『特別代理人』という立場の人を選んでもらう必要があります。
通常は親権者である母親が、子どもの代理人なりますが、その母親も相続人の一人です。
そうなると、母親が一つの遺産分割協議に二つの立場で参加することになってしまいます。
これは、利益相反といってNG行為なのです。
そのため、遺産分割協議のための特別な代理人を選任する必要が出てきます。
裁判所に書類を出す手間、誰かに代理人を頼む手間、いろいろと面倒です。
さらには分割内容について、裁判所が口を出すこともあります。
これからも子供たちと住み続ける自宅や、これからの生活費として必要な夫の預金を下ろすために、けっこう面倒な手続きを踏まなければなりません。
そこで、『すべての財産を配偶者に相続させる』
これだけで良いので、遺言書として残しておけば、この特別代理人選任の手間はカットされます。
わざわざ公正証書にしなくても、自筆で十分です。
(もし時間が許すなら、法務局保管制度くらいは利用しても良いかもしれません)
ちなみに、不動産を買ったタイミングで遺言書を書き残しておく、というのも良いですね。
三井住友信託銀行さんは、住宅ローンを組んだ方向けに、こんなサービスを出したりしてます。
ハウジングウィル
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/housingwill
若い方も是非、検討してみてください。
自分が書いたうえで、ご両親にも話してみると、なかなか話しにくい『親に遺言をどうやって書いてもらえばよいのか…』の切り口にもなるかもしれませんよ。
あなたが遺言を‛書けない’理由⑦
『遺産の分けかたは法律で決められてるんでしょ?』
こういう風に考えて、遺言書に手を付けない方も多いですね。
確かに、民法には 例えば「子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」という風に、分け方(法定相続分)に関する記述があります。
(断言してしまうのは問題ありかもしれませんが)法定相続分というのは、相続で様々な争い事があった時には、最終決着地として、定められたもの、というイメージです。
相続人が全員で合意すれば、法定相続分に関する記述に従う必要はありません。
どんな風に分けても自由です。
法定相続分に縛られる必要はないのです。
全ての財産を配偶者が相続してもいいですし、3人いる兄弟姉妹の取り分に、大きく差をつけても構いません。
でも、選択肢がたくさんあるからこそ、残された相続人たちは、頭を抱えてしまうこともあります。
たくさんある選択肢の中から、相続人全員が納得して、その分け方に同意する必要があるからです。
仮に「法律に従った分け方で」分けてほしい場合でも、きちんと遺言書で「法定相続分にて」という風に、書いておくことをおすすめします。
例えば兄弟姉妹は、法定相続分では原則として平等ですが、本人たちは平等であることを良しとは思っていなことも多々あります。
そういう場合は、「法定相続分で分ける」ということも、スムーズにはいかなかったりします。
子どもたちが、自身の相続をきっかけに仲たがいする、なんてことが無いようにするためにも、きちんと「方針」を遺言書で残してあげましょう。
この記事の執筆者

- 司法書士佐伯啓輔事務所 代表司法書士 佐伯啓輔
-
保有資格 司法書士、民事信託士 専門分野 相続、遺言、生前対策 経歴 司法書士佐伯啓輔事務所代表。 平成24年4月、新横浜に「司法書士佐伯啓輔事務所」を開業。親身で解りやすい解説に定評があり、大手ハウスメーカーや企業福利厚生部門、会計事務所でのセミナー・相談会実績多数。相続発生前の『争いの予防』、相続発生後の『心理的負担の軽減』を様々な角度から提案し、相談者からの信頼も厚い。
横浜・港北で主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
港北・新横浜で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで